2008年3月22日(土)13:30~
小学生対象のワークショップを開催。今回は、竹楽器自作自演のグループ「竹竹(ちくちく)バンブー隊」のみなさんをお迎えし、4種類の竹楽器づくりを子供たちに教えていただきました。
のこぎりで竹を切ることが思いのほか難しかったようですが、こどもたちは夢中になって楽器づくりを体験しました。完成後、場所をご父兄が待つ分館爲三郎記念館の庭内に移し、出来上がったばかりの楽器で演奏を披露。竹竹バンブー隊の音にあわせ、子供たちが思い思いに音を奏でました。その楽しそうな様子をご紹介します。
【今回作成した4種類の竹楽器】
・いやいやぶえ・・・吹くと「イヤイヤ」という音がなる笛(大人気でした!)
・たけたけっと・・・竹竹バンブー隊でいうカスタネット
・エレファントぶえ・・・象の鳴き声のような音がでる笛、形も象のよう
・ほーほーぶえ・・・ちょっと地味な音の笛、でも4種類の中では一番大きな楽器
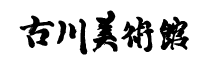
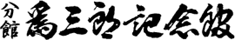
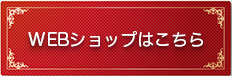

 JA
JA
 EN
EN
 学校関係者の方へ
学校関係者の方へ







































































