愛知大学のキャリア支援センターが開催している「キャリアデザインプログラム」の一環で、『古川美術館見学会~学芸員だけではない美術館の働き方を見てみよう~』をおこないました。
このプログラムは、愛知大学の低年次学生が将来のキャリアビジョンを描くことを支援するプログラムです。
古川美術館の職員がどのような思いを共有してそれぞれの業務に臨んでいるのかといったお話しから、普段はご覧いただけないバックヤードの見学など、わたしたちの仕事を紹介させていただくよい機会となりました。




【告知】古川爲之館長がラジオ出演いたします!

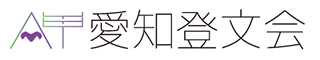
さる12月7日(火)に、愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会(略称:愛知登文会)が主催する「登録文化財保存活用シンポジウム(第2回)」が愛知県立大学サテライトキャンパス(ウインク愛知15階)にて開かれ、当館事務局長の伊藤洋介が、国登録有形文化財である爲三郎記念館の活用事例について発表いたしました。
尚、シンポジウムの様子はNHKニュース「まるっと!」で放映されました。
※NHKプラスに登録すると、1週間は見逃し配信で視聴可能です。
https://plus.nhk.jp/
※12月7日放映分は以下のURLからご覧いただけます。
https://plus.nhk.jp/watch/st/230_g1_2021120749376?playlist_id=1b298d80-7618-423f-9109-f601a947b198
※愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会(略称:愛知登文会)のホームページ
http://www.aichi-tobunkai.org/index.html
※シンポジウムの案内
http://www.aichi-tobunkai.org/pdf_annai/2021/sympo2021-2.pdf
以下の日程で団体様のご来館がございます。ご承知おきのうえご来館くださいませ。
12月1日 10時~
12月2日 13時45分~
12月3日 14時30分~
