※こちらの展覧会は終了いたしました
明治・大正・昭和の三代に渡って日本画壇をリードした横山大観(1868~1958)は、岡倉天心を終生の師と仰ぎ、天心、菱田春草らと日本美術院を創 立、朦朧体と呼ばれる新しい画風を創り出した偉大な巨星です。一方、2007年に没後50年を迎える愛知県出身の川合玉堂(1873~1957)は17歳 で円山四条派の幸野楳嶺に入門、23歳で東京に出て狩野派の橋本雅邦に師事。以来、山村や田園風景など日本の自然とともに生きる人々の生活を主題に生涯を かけて美しい日本の風景を探し求め、描き残しました。院展同人として活躍した川端龍子(1885~1966)は、青龍社を主宰し会場芸術を主張するなど、 日本画の世界に新風を巻き起こした画家でした。このような異なった環境、流派で活躍し、目指すものを異としたこの三巨匠ですが、1952(昭和27) 年~57(昭和32)年に「雪月花展」「松竹梅展」を開催し、三人で合作を制作するなど幅広い芸術活動を展開させました。本展覧会では、三人が競演した雪 月花展、松竹梅展にて出品された作品を中心に、三巨匠の作風を一堂に介し、それぞれが目指した芸術に迫ります。
| 期間 | 2007年10月20日(土曜日)~12月16日(日曜日) 一部展示変えあり 前期: 10月20日(土曜日)~11月18日(日曜日) |
|---|---|
| 休館日 | 毎週月曜日 |
| 会場 | 古川美術館 |
| 開館時間 | 午前10時~午後5時 (入館は午後4時30分まで) ※金曜日(10月26日、11月2日、9日、16日、23日、30日、12月7日、14日)は午後8時まで開館(入館は7時30分まで) |
| 料金 | 大人1,000円 / 高・大学生500円 / 小・中学生300円 ※古川美術館、爲三郎記念館共通券となります。
|
| 主催 | 財団法人古川会 古川美術館、中日新聞社 |
| 後援 | 愛知県教育委員会 / 名古屋市教育委員会 / スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 |
爲三郎記念館 同時公開 「茶の湯 内田繁の世界」
インテリアデザインを通して日本文化を研究し、家具からブティックなどの商業空間まで、様々なデザインを手掛ける内田繁氏。氏は日本文化の根元を茶の湯に見出し、日本のデザインの可能性を追求し続けています。
そして本年度春、内田氏は紫綬褒章を受章しました。本章は、インテリアデザイナーとしては初めての受章であり、これはインテリアデザインという分野を日本に確立した功績によるものです。氏は現在も第一線で活躍し続けています。
今回は、その内田繁氏が、茶事を目的に昭和初期に建てられ、伝統的な数寄屋空間をとどめる爲三郎記念館を演出します。キーワードは「茶の湯」。日本文化の根底に流れる茶の湯は、氏の手によってどのように表現されるのでしょうか。内田繁デザインの茶の湯道具と数寄屋空間の総合演出によって実現する茶の湯の世界、そしてインテリアデザイナー内田繁の世界をお楽しみください。
内田繁氏 略歴
| 1943年 | 横浜生まれ | |
|---|---|---|
| 1966年 | 桑沢デザイン研究所卒業 | |
|
東京造形大学、
桑沢デザイン研究所客員教授 毎日デザイン賞、第一回桑沢賞、 芸術選奨文部大臣賞等受賞、‘07春の紫綬褒章受章 代表作に六本木WAVE、山本耀司のブティック一連、 科学万博つくば‘85政府館、京都ホテルのロビー、 福岡のホテル イル・パラッツオ、神戸ファッション美術館、 茶室「受庵・想庵・行庵」、広島オリエンタルホテルなど メトロポリタン美術館、サンフランシスコ近代美術館、 モントリオール装飾美術館、デンヴァー美術館等に 永久コレクション多数 |
||
期間限定展示 内田繁 茶室「受庵」
※本茶室は、屋外展示のため、期間限定の展示となります。なお、作品保護上、天候により展示を変更する場合がございます。予めご了承ください。
・10月20日(土)、21日(日)
・11月16日(金)※両館、夜間開館
・11月23日(金)※両館、夜間開館
・11月24日(土)、25日(日)
・12月 7日(金)※両館、夜間開館
・12月 8日(土)、9日(日)
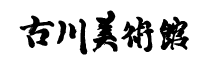
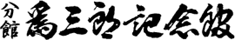
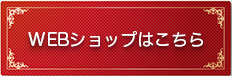

 JA
JA
 EN
EN
 学校関係者の方へ
学校関係者の方へ