※こちらの展覧会は終了しました。
古川美術館開館25周年記念として、中部洋画壇を牽引した加藤金一郎(1921-1997)と丹羽和子(1924-2014)の作品を展覧します。
加藤金一郎は国際的に活躍した洋画家・猪熊弦一郎に師事し、独自の芸術を目指した新制作協会を中心に活動しました。鮮やかで豊かな色彩と大胆で躍動的な造形で、人の心を打つ力強い自然を描き出します。1970年代からは日本の各地の祭りをはじめ欧州、中南米、日本の各地の風景を描いた作品を次々と発表しました。エネルギーに満ち溢れた作品は加藤の代表作となり、多くの後進の画家たちに強い衝撃を与えています。その加藤と共に中部洋画壇の中心的存在であった丹羽和子は、女子美術大学卒業後に加藤と結婚し、新制作協会を舞台に活動しました。生涯《女》《人間の内面》を鋭い視線でとらえた作品は、大胆で強烈な個性を放っています。一方で新聞連載漱石名作シリーズの挿絵を手掛け、エスプリのきいた親しみやすい作風で多くの人々を魅了してきました。古川美術館初代館長の自伝「この道・古川爲三郎伝」(中日新聞夕刊 1987年全48回連載)の挿絵を担当し、古川美術館ともゆかりの深い画家です。
本展では、加藤の代表的な祭りシリーズ、南米に生きる人の息遣いまでを見事に描き出した作品、自然の心を描き出した中部山岳シリーズを紹介します。丹羽は、生涯のテーマとした女の業・因縁や宿命をテーマにしたものや、シンプルな表現で人間の本質と深部に迫った作品を展示し、時代の最先端を鮮烈に描き出した独自の世界を紹介します。
ともに絵に生きた加藤金一郎と丹羽和子の、偉大なる足跡を辿ります。
| 会期 | 平成28年8月20日(土)~10月10日(月・祝) |
|---|---|
| 休館日 | 月曜日 ※ただし9月19日(月・祝)開館、翌20日休館 |
| 主催 | 公益財団法人古川知足会 |
| 協力 | 株式会社アートランド |
| 後援 |
愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会、中日新聞社 |
| 開館時間 | 午前10時~午後5時 (入館は午後4時30分まで) |
愛知県立芸術大学創立50周年関連事業
爲三郎記念館特別展「磯田皓と12人の作家たち」
「芸術はDo!だ」。これは、固まることないモノづくりを信条とする磯田皓の言葉です。愛知県立芸術大学名誉教授であるデザイナー磯田皓。磯田皓のデザイン観。それは己をデザインすること。生をデザインすること。美術も音楽もいかなることも全ての表現行為はその一端であること。その考えから生まれた彼の人生を彩るのは、狂言肩衣のデザイン、郵便切手のデザイン、イラストレーション、書籍装丁、絵画、書、エッセイなどグラフックにとどまらない多岐に渡るデザインの数々です。それらの仕事、作品はどれも知的でシンプル且つ時空を越えた美しいものです。本展では、磯田自身の秘蔵作品も含めてデザインの神髄をご覧いただきます。
また、磯田の教えを受け様々な分野で活躍する12人のアーティストの作品も同時に展覧し、空間を演出します。作家たちがみせる出会い、爲三郎記念館の瀟洒な空間との響きあいをどうぞお楽しみください。
| 会期 | 平成28年8月20日(土)~10月10日(月・祝) |
|---|---|
| 休館日 | 月曜日 ※但し9月19日(月・祝)開館、翌20日休館 |
| 主催 | 公益財団法人古川知足会 |
| 協力 | 皓の会(記念館のみ) |
| 後援 |
愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会 中日新聞社 |
| 開館時間 | 午前10時~午後5時 (入館は午後4時30分まで) |
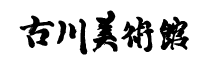
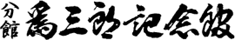
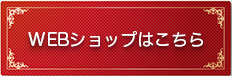

 JA
JA
 EN
EN
 学校関係者の方へ
学校関係者の方へ